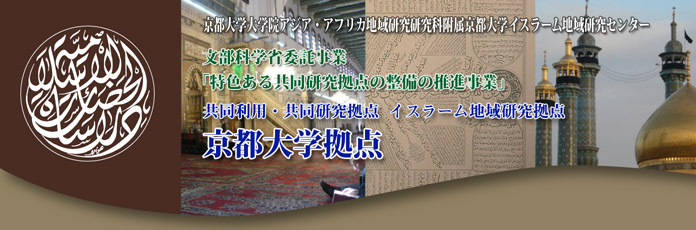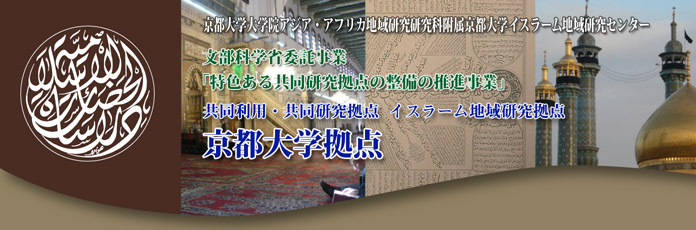「イスラーム法とテクノロジー」研究会
2011(平成23)年度第2回研究会報告書
(10月21日 於明治大学) (2011年10月23日作成)
2011年10月21日(金)、明治大学駿河台キャンパス・リバティタワー16階1167教室において、「イスラーム法とテクノロジー」研究会の2011年度第2回目(通算9回目)の研究会が開催された。出席者は報告者である米岡大輔、清水美穂、および研究分担者の川本正知、研究協力者の川本智史に加えて、秋葉淳、岩田昌征、大谷悠己、奥美穂子、小林馨、佐治奈通子、成地草太、長谷部圭彦、林佳世子(敬称略)および研究代表者の江川ひかりの計14名であった。
報告 16:30~17:50 米岡大輔氏(日本学術振興会特別研究員)
「ハプスブルク治下ボスニアにおける進歩的ムスリムと教育問題」
米岡大輔氏の報告は、ハプスブルク統治下のボスニアにおいて進歩的ムスリムと呼ばれた知識人層がイスラーム教徒を
めぐる教育問題についていかなる議論を展開したのかに焦点をあてた。1878年のベルリン会議以後、共通蔵相管轄下におかれたボスニアでは、伝統的な宗教教育とボスニア内外のハプスブルク帝国側の学校教育をもうけた知識人層が進歩的ムスリム(Napredni Muslimani)としてイスラーム教徒を取り巻く教育問題にさまざまな形で提言をおこなった。進歩的ムスリムに関する従来の研究は、一方では「ボスニア人」意識の創出者であるという視点が強調され、とくに1990年年代以降は「ボスニア人」としての民族的普遍性の確立を目指した人びととして論じられること、すなわち遡及的・単線的な「ボスニア人」民族史が論じられてきた。他方、ボスニアの教育史研究では、同時代のボスニアにおけるイスラーム教徒の学校教育の実態を解明する中で、帝国統治とイスラーム教徒の対立関係を強調し、教育状況における保守的・後進的側面のみを浮き彫りにしようとする傾向があったという。このような研究動向に対して米岡氏は、「民族」理念に重きをおく進歩的ムスリムが,イスラーム教徒初等教育(メクテブ)の在り方に関していかなる意見を発し、それがボスニアにおいてどのような展開を遂げたのかという問題を、主として文芸誌『ベハール(Behar 花)』(1900-1911)に依拠して解明した。共通蔵相カーライは、ボスニア統治にあたり、ムスリム住民を制度として管理化するために、1882年にはレイス・ウル・ウレマー職とその諮問機関ウレマー・メジュリスを創設した。さらにカーライは、全住民がボスニア生まれのひとつの「民族」であるとする「ボスニア主義」という理念を構築し、この統治理念の普及装置としての公立小学校へイスラーム教徒通学者を増加させようと1892年、改革メクテブを創設した。これに対して、モスタル出身のジャヴィチを指導者とする地主層・宗教家は、スルタンの権威への帰属と従来のメクテブ増設を希求する嘆願運動を1899年から本格化させた。このような教育における2つの潮流の中で進歩的ムスリムは、「教育言語として民族言語を導入しなければ、教育における本当の進歩はありえない」と論じ、メクテブでも民族言語で宗教を学習することの重要性を主張し、アラビア文字アレビッツァの利用も視野に入れるべしと提案した。その後、1908年10月の併合後、1909年に制定されたイスラームに関する自治法において、レイス・ウル・ウレマーを頂点とした宗教・教育制度の自治的運営承認された。この併合から第一次世界大戦前後のボスニアを取り巻く情勢の中で、イスラーム教徒は学校教育を通じてボスニアのムスリムとしての民族意識を保持していくこととなり、その主導的集団として、1914年にレイス・ウル・ウレマーに選出されたチャウチェヴィチを中心に、現実路線を選択した進歩的ムスリムの存在があったと位置づけた。
18:00~18:55 清水美穂氏(バーニャ・ルーカ マルコポーロクラブ講師)
「ボスニア・ヘルツェゴヴィナのレイス・ウル・ウレマー、ムスタファ・チェリチをめぐる論争」
清水美穂氏の報告は、現代のボスニアでイスラーム法を市民生活に浸透させようとするレイス・ウル・ウレマー、ムスタファ・チェリチ(1999年より現職、現在2期目)の戦略とその反響から、現在、そしてこれからのボスニア・ヘルツェゴヴィナを考えることを目的とした。そもそも清水氏ご自身が旧ユーゴに留学していた78年から81年まで、「レイス・ウル・ウレマー」という役職名を聞いたことはなかったという。また、ユーゴスラヴィア解体が始まるまでは、ボスニアにおいてもその存在はさほど大きなものではなかった。しかし、現在、ボスニアの中でもイスラーム化が進む地域においては、チェリチの率いるイスラーム・コミュニティはムスリムの支持を背景に「シェリアト(シャリーア)を憲法の一部に」という意見を堂々と主張するようになってきている。彼らはボスニアの初代大統領であったアリア・イゼトベーゴヴィチ著『イスラーム宣言』(1970年発表後当局によって出版が禁じられた)の思想を巧みに利用している。実際、チェリチは2009年、ゼニッツアでシャリーアにのっとった20組のイスラーム集団結婚式を500人の招待客を招いて挙行した。ちなみにこのときの資金は、故カダフィ大佐から援助されていたという。また、最近チェリチは、自分自身を「レイス・ウル・ウレマー」よりも「グランド・ムフティ」と称することが多い。彼はこれまでにもましてより国際的な活動をめざしており、2011年2月には、ムフティはもちろんラビ、司祭、主教とさまざまな宗教の指導者を率いてアウシュヴィツを訪問し、「シャリーアが人びとの生活に生かされれば、アウシュヴィツやスレブレニツァのような悲劇は起こらなかったのだ」と演説した。このように資金とメディアを有効に利用し、近い将来全欧ムフティ会議の長を目指すチェリチは、「ボスニアのレイス・ウル・ウレマー」から「世界のグランド・ムフティ」へというグローバル化に乗じた戦略に出ようとしている。北アフリカと中東の情勢が刻々と変わる中で、特異な立場に立つチェリチの動向を今後も注視していく必要があることを指摘された。
質疑応答も非常に活発で時間が足りないほどであった。とくにお二人の発表へ川本正知氏から出された「美しいシャリーア」「シャリーアにのっとった結婚式」という時のシャリーアとは何を意味するのかという質問は、今後、本研究会でいっそう議論を深めていく課題となった。同時にボスニアにおけるイスラーム教徒・社会に関する研究は、本研究会のようにハプスブルク、ボスニア、アラブ、オスマン等の研究者が共同で進めていくことによってはじめて歴史の内実を解明できることが再確認された。本研究会が終了する2013年度末までに時間が許せば、再度、上記の議論を深める機会をもちたい。(江川ひかり)
KIASユニット1、共同利用・共同研究拠点 イスラーム地域研究拠点「京都大学イスラーム地域研究センター」共催WS「イラン・イスラーム革命30周年――中東諸国への政治・経済的インパクト」
(2月28日 於京都大学)
発表題目:「イラン・イスラーム革命から30年――研究史とインパクト」
発表者:松永泰行
発表題目:「イスラーム革命とサダムの30年――イラクの遅れてきた革命」
発表者:酒井啓子
発表題目:「シリア――東アラブにおける覇権追求と革命イランの戦略的パートナーシップ」
発表者:青山弘之
発表題目:「革命の意味をめぐって――シリア・イスラーム革命とイラン・イスラーム革命」
発表者:末近浩太
発表題目:「革命後におけるイランと湾岸アラブ諸国との経済関係」
発表者:細井長
発表題目:「オマーンとイラン革命」
発表者:松尾昌樹
発表題目:「湾岸安全保障とシーア派ファクター」
発表者:保坂修司

本シンポジウムは、本年がイラン・イスラーム革命から30年を迎えたことを契機に、日本における現代中東の専門家が、それぞれの地域に及ぼした革命の政治的・経済的な影響とその帰趨を報告・議論するために開催された。以下、各報告の概要と議論を簡単に振り返りたい。
小杉泰氏による開会の辞では、フランス革命、共産主義革命といったこれまでの近代革命がいずれも「世俗主義」に立脚するものであったのに対し、イラン・イスラーム革命は「宗教革命」であったところに世界史的意義があり、「革命」のもつコノテーションの違いに注意を払いつつイラン・イスラーム革命のもつアクチュアリティーを再確認すべきとの認識が寄せられた。
続く末近浩太氏による趣旨説明では、革命の持つインパクトを「認識」と「構造」に二分し、西洋近代にとって革命は「想定外」であったのに対してムスリムにとっては「想定内」にあったこと、また「構造」を国内、地域、国際という3つのレベルで整理し、各地域、各時代、各ディシプリンからイラン革命を見ると同時に、逆にイラン革命からそれぞれの地域の研究を説き結ぶ必要があることが指摘された。
このように議論の素地がなされた上で、松永泰行氏による第1報告「イラン・イスラーム革命から30年――研究史とインパクト」は、とりわけて同国と国外それぞれに革命の及ぼしたインパクトについて考察を加えるものとなった。そこでは、革命の持つ多重的な意味やこれまでのイラン政治史の整理に主眼が置かれたが、イランを専門とする氏がイスラーム革命の現在的帰趨について「イランの政治空間に弊害をきたしている」と消極的に総括したことは印象的であった。
続く酒井啓子氏による第2報告「イスラーム革命とサダムの30年――イラクの遅れてきた革命か?」は、隣国イラクの視点から革命について分析を施すものであった。そこでは、イラン・イスラーム革命が勃発した同年にイラクでフセイン政権が誕生したことのもつインプリケーション、同政権が革命にどのように対処した/しようとしたのか、などが議論されたが、特にサダム政権が革命を宗教的にとらえることなく、経済的な合理性や世俗的なナショナリズムの視点から主に意味づけていたと氏が指摘しているあたり、真摯に受け止める必要があろう。
報告者:(平野淳一・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)
イラン革命のインパクトについて、青山氏と末近氏はレバノン・シリアの地域動態に対する影響を中心に議論が行われた。
青山氏はシリアにとってイラン革命は、政権が内外の不安定要因の牽制を可能にさせるとともに、「戦略的均衡」を図り、中東における地域大国へと変貌する契機であったと位置づける。
シリアは外的にはエジプトとイスラエルによるキャンプ・デーヴィッド合意によって、対イスラエル戦略の転換を迫られるとともに、内的にはシリア・ムスリム同朋団の破壊かつ活動によって社会発展が阻害されていた。そのなかで発生したイラン革命をシリアは「国民解放」という側面を評価することで、国内のシリア・ムスリム同朋団をイデオロギーの正当性の問題として孤立させ、その殲滅に成功した。また不安定中東国際関係の中でイランとのパートナーシップを構築することで、「戦略的均衡」を図った。しかしその一方でシーア派組織の支援を通じてレバノンに干渉するイランと、レバノンにおいてレバノンにおけるパワーブローカーとしての地位を獲得し、対イスラエル武装闘争の主導権を目指すシリアの関係は必ずしも協力関係とは言いがたい側面をはらんでいた。青山氏は両義的な関係からさらに踏み込んで、現状のシリア国内の見解として「イラン脅威論」の陰に隠れて、東アラブ地域における影響を強化するという関係であると分析した。
続いて末近氏はレバノンのシーア派組織ヒズブッラーの誕生背景について他のシーア派組織との関連を踏まえながら、その史的展開を明らかにした。レバノンのシーア派組織の古参であるアマルはバーザールガーン革命暫定政府と人的資源の問題も含め蜜月状態にあった。しかしアメリカ大使館占拠事件を背景にバーザールガーン政権がイランの政治舞台から退潮し、イラン国内ではイスラーム共和党が勢力を拡大した。こうした革命後の政権展開は次第に革命政府の方針とアマル指導部の方針の間に摩擦を生じさせた。加えてアマル内部でも指導方針をめぐって内部分裂が起こり、勢力を衰退させていった。こうしたレバノンのシーア派勢力の騒乱の中でヒズボッラーが登場し、イランの革命防衛隊(パースダーラーン)との連携により勢力を拡大していった。末近氏はこれらの展開を踏まえ、ヒズボッラーの位置づけに関し、流動的な国際関係と流動的な組織の構成体など単に「イランの手先」に還元できない問題を明らかにするとともに、本発表を結成時と今日との間の連続性と断続性を明らかにする作業の一環であると位置づけた。
報告者:(黒田賢治・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)
細井氏の発表は、イラン革命を契機としたイランと米国の関係悪化、さらにはイランに対する様々な経済制裁がとられるなかで、イランの貿易においてドバイの果たした役割に着目するものであった。発表では、様々な経済的指標やドバイを経由する対イラン貿易のメカニズムを示し、経済制裁の陰では先進諸国やイランの隣国がドバイからの再輸出という方法でイランとの交易を継続してきたと論じた。
また、海外直接投資の問題について触れ、この分野においてもドバイを利用した投資活動が活発に行われている可能性を指摘した。イランの直接投資をめぐっては、国際連合によるイランへの金融制裁に伴って、カントリーリスク(商業リスク以外に生じるおそれのある損失を示す指標)が悪化し、外国資本の投資意欲が低下した。このような状況のなかで、ドバイに設置した特定目的会社(SPD)を通じて、イラン企業がUAE企業として行っている経済活動がどの程度存在するのかについても、今後さらに検討していく意義があると述べた。
イランとUAEの経済関係は、20世紀の初頭にイラン系商人がドバイへ移住したころから密接なものとなり、それ以来、ドバイは対イラン貿易における交易拠点としての地位を確立した。そして、イラン・イスラーム革命とそれに続くイラン・イラク戦争から今日に至るまで、対イラン経済制裁のなかでUAEとイランの密接な経済関係を利用した経済活動が行われていることが報告された。
続いて松尾氏により報告がなされた。
イラン革命前のオマーンは、60年代以来内戦状態にあった。オマーンの共産主義化を恐れる国々は内戦にも関与しており、革命前のイラン政府は内戦終結宣言が出された1975年以降もイラン軍をオマーンに駐留させていた。革命後、軍は撤退されたものの新政府とオマーンの外交関係は継続されていた。
一般的に、オマーンにおけるイラン革命の影響は、他の湾岸諸国と比較して小さかったといわれている。その理由として、オマーンとイランはホルムズ海峡を共有しているために敵対する必要がないという議論や、オマーンにおけるシーア派人口の割合が他の湾岸諸国と比較すると小さかったためという説明などが提示されてきた。
上記のような見解に対して、オマーンにおいて革命の影響が小さかったことの「積極的」理由を見出そうというのが本発表の目的であった。そのために、「湾岸型エスのクラシー」、および「イスラームのオブジェクト化」という2つの議論を用いて革命当時のオマーンの状況が検討された。
はじめに、「イスラームのオブジェクト化」についていえば、当時のオマーンでは近代教育制度が開始されたばかりであり、集合的アイデンティティや、他者としてのシーア派という関係は成立していなかったことが指摘された。さらに、インド系のシーア派住民が人口においても経済力においても大きな影響力を有していた。そのため、従属集団としてのシーア派というカテゴリーが存在しなかったといえよう。
「湾岸型エスノクラシー」についていえば、70年代のオマーンではアラブ系オマーン人が支配集団を形成する途上にあり、官僚機構には近代教育を受けたザンジバル系住民が多く登用されている状況であった。また、1968年に開始された石油の生産量は他の湾岸諸国のなかでも規模が小さく、さらに、アラブ系オマーン人内部においても階層分化がみられることなどから、オマーンにおける「湾岸型エスノクラシー」は完成しなかったと結論づけられている。
保坂氏の発表では、湾岸諸国の安全保障体制とシーア派ファクターとの相互関係について、広い視点からの分析がなされた。本報告では、発表内容を簡単に紹介したい。
湾岸の小国にとって、安全保障上もっとも重要なことは、独立の維持、および現体制維持のために周辺諸国や大国との合従連合や協力体制をいかに図ってゆくかという点にある。20世紀初頭においては、オスマン朝と英国が地域の安全保障にとって重要なアクターとなっていた。戦間期にあたる1930年代には領土的変更は一時停止され、英国がこの地域における覇権を握っていた。ところが、1970年代になると英国は撤退をはじめ、英国に代わって米国がこの地域の安全保障にとって重要な役割を果たすようになった。
しかし、イラン・イスラーム革命によって、イランとサウディアラビアを二本柱とする米国の対中東体制が崩れた。そして、イラン革命の影響を恐れた湾岸の小国とサウディアラビアは湾岸協力会議(GCC)を結成し、米国はGCC諸国やイランと戦争を展開するイラクとの協力体制を強めた。いずれにせよ、湾岸諸国のシーア派ファクターは、地域大国であるイラン、イラクの影響を受けて顕在化する傾向がある。
GCC諸国における対イラン関係が大幅に改善されたのは、サウディアラビアのシーア派問題をめぐってイランとサウディアラビアが合意を形成した1993年のことであった。これによって、革命の輸出がストップされ、スンナ派とシーア派との共存の時期が訪れた。これは、歴史的にみても、ペルシアと対岸のアラブ諸国の関係が(少なくとも政府レベルにおいて)良好になった時期として捉えられる。
2000年代以降の湾岸安全保障とシーア派ファクターについていえば、現在GCCそれ自体は大きな対立を抱えていないといえる。その一方で、湾岸地域の周辺ではレバノンやシリアにおけるシーア派ファクターのインパクトが強まっており、イランはその動きと大きく連動している。このような状況に対して、湾岸諸国は慎重な態度を取っているのが現状である。
報告者:(平松亜衣子・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)