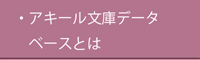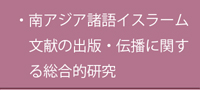「アキール文庫データベース」とは、科学研究費補助金基盤研究(B)「南アジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」の成果の一つとして、京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科が所蔵する2万6千点を超える(書籍・雑誌のみならず、新聞、パンフレットを含む点数)南アジアのイスラームに関する文献=「アキール文庫」をデータベース化したものです。このプロジェクトの遂行にあたっては、京都大学アジア研究教育ユニットの「世界最高峰の現代アジア・日本研究の教育研究拠点形成-京都大学アジア研究クラスターと国際連携大学院プログラム-」の資金援助を得て、アキール文庫の元来の所有者であるモイーヌッディーン・アキール博士(パキスタン・カラチ大学元教授)の招聘を2回にわたって行い、より学術的に価値の高いデータベースを構築するべく、議論を行ってきました。
「アキール文庫データベース」は通常の書誌データベースに加え、「時空間検索」を行うことで「文献の出版・伝播」に関する分析を支援するツールとしても機能します。機能の詳細に関してはマニュアルをご覧下さい。
「アキール文庫データベース」は通常の書誌データベースに加え、「時空間検索」を行うことで「文献の出版・伝播」に関する分析を支援するツールとしても機能します。機能の詳細に関してはマニュアルをご覧下さい。

「南アジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」は、宗教文化の媒体でありかつ社会の公器という二面性を持つ文献(出版物)を対象とし、前近代から近現代へと移行するなかで変容した宗教と社会の関係を問う実証的基盤をつくることを目的としています。本研究では、近現代南アジア・イスラームがもつ固有性/普遍性を実証的に見定めるために、南アジア・イスラームの顕著な特徴である、宗教概念と結びついた印刷文化に焦点を当て、印刷文献がどのように選定されたのか、それらがどこでどのようにして印刷されたのか、そしてそれらがいかなる経路で伝播したのか、の三点、つまり「近現代南アジア・イスラームが創出した出版文化の総体」の研究および情報蓄積を行います。
学術的背景
全世界のムスリム人口のほぼ三分の一におよぶ五億人以上のイスラーム教徒が居住する南アジアはもっとも多くのムスリムを有する地域です。また地理的には東アジア・東南アジア・中央アジア・中東・東アフリカと接し、それら地域の中心に位置し、人・モノ・概念の流通においてそうした諸地域を繋ぐ大きな拠点の一つとして機能してきました。他方、ヒンドゥー教・仏教・イスラームなど多くの宗教が混在・混淆するという点に、他の地域にない南アジアの特色を見出すことができます。多文化・多宗教的状況下にありながら、ある意味でイスラーム世界の中心に位置するといういささか相矛盾する状況が南アジア・イスラームに大きな影響を与えてきたことは疑いを容れません。特に近代以降、こうした状況を背景として中東と違った意味で南アジアがイスラーム的諸概念の発信地となったことは忘れられがちですが、宗教としてのイスラームのあり方、さらには現在のグローバル化したイスラームを考察するうえで欠くべからざる対象の一つです。しかしながら、研究対象として南アジア・イスラームがもつ大きな可能性に比して、国内外を問わず十分に注目されていないと言わざるをえません。
南アジア・イスラームが学問的対象として確たる地位を獲得していない理由として、「二重の周縁化」がしばしば指摘されています(山根聡「南アジア・イスラーム研究の意義と眺望」『イスラーム世界研究』第一巻一号)。一つは南アジア・イスラームが非アラブ圏に属していることに起因する周縁化です。アラビア語がイスラームの基本的言語である、イスラームの中心は中東にある、との単純な理解にもとづくならば、中東に位置せず日常言語としてアラビア語を用いない南アジア・イスラームが研究対象として周縁化されるに十分でしょう。第二の周縁化は、南アジアの多文化・多宗教状況のなかでつねに多数派であるヒンドゥー教/ヒンドゥー教徒と比較されることによって生じます。南アジア・イスラームの主要言語の一つであるウルドゥー語の(学術語としての)成立が比較的後代になるという事情にもより、サンスクリット語仏教文献が古典学において確固たる研究対象になっているのに対して、南アジアのイスラーム文献がそうした地位を得ていないことも第二の周縁化を引き起こす要因と考えられます。この二重の周縁化をいかに克服するのか。これが南アジア・イスラーム研究の最大の課題です。
13世紀以降のデリー・スルタン朝、16世紀から19世紀半ばまでのムガル朝にみられるように南アジアにおけるイスラームは前近代においても重要な要素でしたが、前述のように南アジア・イスラームの個性が際立ってきたのはムガル朝末期から英領インド期を経て、独立運動期、独立後ヒラーファト運動期へと続く近代初期以降です。近代以降の南アジア・イスラームの展開を支えたのが出版活動、出版文化であることは一部の学者が主張しはじめたばかりであり、学界に浸透していないのが現状です(cf. Moinuddin Aqeel, "Commencement of Printing in the Muslim World: A View of Impact on Ulama at Early Phase of Islamic Moderate Trends" in So YAMANE (ed.), Towards Multilateral Elucidation of Islamic Trends in South Asia: History, Thought, Literature, and Politics, 2010.)。本研究は、近現代南アジア・イスラームを正しく評価するため、つまり前述の二重の周縁化を克服するための基盤を築くために、南アジア・イスラームをめぐる出版文化を調査し、データを蓄積することにしました。
本研究で明らかになった内容
本研究が対象とする南アジア諸語イスラーム文献(出版物)には南アジア・イスラーム、ひいては南アジア独特の事情が反映しています。イスラーム世界では写本の伝統が強かったため、自発的に出版を本格的に導入するのは、ヨーロッパや中国などと比べてかなり遅く、19世紀末から20世紀初めにかけてです。南アジアでも事情は似ていますが、出版の導入はエジプト、トルコ、イランなどより若干早く、19世紀初めにさかのぼります。これは、インドのムスリムが自発的に出版を導入したのではなく、1800年に東インド会社がカルカッタにイギリス人書記官養成機関であるフォート・ウィリアム・カレッジ(Fort William College)を設立し、南アジアの現地語および習慣を学習する目的で教科書を編纂する過程において「ヒンドゥスタニー・プレスHindustani Press」が同時に設置され、アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語などの刊行物が大量に発刊されたためでした。『アラビアン・ナイト』の底本として定着しているのも、このカレッジから1802年以降に刊行された版なのです。学術語としてのウルドゥー語が前面に出てくるのはこうした出版文化を背景としています。そしてその事情により、図らずも南アジアはイスラーム世界の先進地域となるのです。それ以前に南アジアで学術語として使用されたのは主にペルシア語、少し頻度を落としてアラビア語であり、デリー・スルタン朝、ムガル朝の支配層がテュルク系民族であったことからテュルク系チャガタイ・トルコ語が若干使用されました。
このような背景を元に、本研究では、次の3つの問いをたてました。
(1)出版文化が生じることによってペルシア語・アラビア語などからウルドゥー語へと主役が移る際に、いかなる文献がウルドゥー語をはじめとする南アジア諸語に翻訳され、出版されたのか。これは、アラビア語やペルシア語(そしてチャガタイ・トルコ語)文献の何が取捨選択されて南アジア・イスラームの伝統として受け継がれたか、という問いにつながります。
(2)どの出版社でいかなる南アジア・イスラーム文献は、南アジア諸語のうちのどの言語を使って出版されてきたのか、そしてそうした印刷所はだれが担っていたのか、そうした出版物は何を対象としているのか。
(3)19世紀初めから出版されてきた南アジア諸語イスラーム文献は、どこに流通したのか
(1)については、宗教書や物語文学が代表的なものだということが明らかになりました。
アキール文庫に所蔵されているウルドゥー文学史(Jamil Jalibi, Tarikh-e Adab-e Urdu 等)の一連の研究書によって、南アジアでは15~16世紀ごろから、アラビア語やペルシア語の宗教書がrisalaの体裁で翻訳されていたことがわかります。
また、物語文学に関しては、元来サンスクリット語で書かれたSukasaptatih (『鸚鵡七十話 インド風流譚』田中於菟弥訳、平凡社東洋文庫、1963)が、14世紀初めにペルシア語に翻訳されてTuti Namehとなりますが、前述のとおり、19世紀初めにイギリス人が簡明な北インドの口語体(ヒンドゥスターニー語=ウルドゥー語)の教科書を編纂するうえで、これをハイダルバフシュ・ハイダリー(Haidar-Bakhsh Haidari)という文人を使ってTotaaa Kahani『鸚鵡物語』として刊行させたことなどが知られています。
アキール文庫には、こうしたアラビア語やペルシア語からウルドゥー語への翻訳の過程に関する文献、研究書が豊富に所蔵されているほか、南アジアで執筆されたトルコ語文献、ペルシア語文献(スーフィー伝記、詩集等)も所蔵されています。
また、ムガル朝期には、上に述べたペルシア語・アラビア語・トルコ語だけでなく、サンスクリット語からの翻訳もさかんに行われていたのでした。
現代の南アジアが、南アジア固有の諸言語や英語による多言語空間である、という事実は周知のことですが、実は1世紀近くさかのぼると、アラビア語、ペルシア語、トルコ語といった西アジアの諸言語もこの多言語空間に含まれつつ、それらの翻訳活動が行われていたことが、本文庫所蔵の文献を検証することによって明らかとなりました。
(2)については、本データベースに時空間検索の機能を備えることにより、個別の事例を調べることが可能となりました。
この際、ムスリムの経営する出版社からイスラーム文献が出版されるとは限らず、またムスリムが必ずムスリムの言語と見なされるウルドゥー語やベンガル語で文献を出版するとも限らないといった例があることに留意しなければなりません。ヒンディー語で書かれ出版されたイスラーム文献が少なからず存在するからであり、アキール文庫にはこのような書籍も少なからず収められています。
(3)については、東南アジアが最も多く流通した地域ですが、ほかにもアラブ諸国や東アフリカなどが含まれることが分かりました。
アキール文庫にある19世紀半ば以降のイスラーム復興に関する研究書によって、デーオバンド学院への東南アジアからの留学生が、ウルドゥー語で学んだ知識を祖国に持ち帰り、復興運動を展開した経緯が明らかとなるうえに、マウドゥーディーの書簡集等によって、彼の著作がアラビア語に翻訳されたことも実証的に示すことができます。
学術的背景
全世界のムスリム人口のほぼ三分の一におよぶ五億人以上のイスラーム教徒が居住する南アジアはもっとも多くのムスリムを有する地域です。また地理的には東アジア・東南アジア・中央アジア・中東・東アフリカと接し、それら地域の中心に位置し、人・モノ・概念の流通においてそうした諸地域を繋ぐ大きな拠点の一つとして機能してきました。他方、ヒンドゥー教・仏教・イスラームなど多くの宗教が混在・混淆するという点に、他の地域にない南アジアの特色を見出すことができます。多文化・多宗教的状況下にありながら、ある意味でイスラーム世界の中心に位置するといういささか相矛盾する状況が南アジア・イスラームに大きな影響を与えてきたことは疑いを容れません。特に近代以降、こうした状況を背景として中東と違った意味で南アジアがイスラーム的諸概念の発信地となったことは忘れられがちですが、宗教としてのイスラームのあり方、さらには現在のグローバル化したイスラームを考察するうえで欠くべからざる対象の一つです。しかしながら、研究対象として南アジア・イスラームがもつ大きな可能性に比して、国内外を問わず十分に注目されていないと言わざるをえません。
南アジア・イスラームが学問的対象として確たる地位を獲得していない理由として、「二重の周縁化」がしばしば指摘されています(山根聡「南アジア・イスラーム研究の意義と眺望」『イスラーム世界研究』第一巻一号)。一つは南アジア・イスラームが非アラブ圏に属していることに起因する周縁化です。アラビア語がイスラームの基本的言語である、イスラームの中心は中東にある、との単純な理解にもとづくならば、中東に位置せず日常言語としてアラビア語を用いない南アジア・イスラームが研究対象として周縁化されるに十分でしょう。第二の周縁化は、南アジアの多文化・多宗教状況のなかでつねに多数派であるヒンドゥー教/ヒンドゥー教徒と比較されることによって生じます。南アジア・イスラームの主要言語の一つであるウルドゥー語の(学術語としての)成立が比較的後代になるという事情にもより、サンスクリット語仏教文献が古典学において確固たる研究対象になっているのに対して、南アジアのイスラーム文献がそうした地位を得ていないことも第二の周縁化を引き起こす要因と考えられます。この二重の周縁化をいかに克服するのか。これが南アジア・イスラーム研究の最大の課題です。
13世紀以降のデリー・スルタン朝、16世紀から19世紀半ばまでのムガル朝にみられるように南アジアにおけるイスラームは前近代においても重要な要素でしたが、前述のように南アジア・イスラームの個性が際立ってきたのはムガル朝末期から英領インド期を経て、独立運動期、独立後ヒラーファト運動期へと続く近代初期以降です。近代以降の南アジア・イスラームの展開を支えたのが出版活動、出版文化であることは一部の学者が主張しはじめたばかりであり、学界に浸透していないのが現状です(cf. Moinuddin Aqeel, "Commencement of Printing in the Muslim World: A View of Impact on Ulama at Early Phase of Islamic Moderate Trends" in So YAMANE (ed.), Towards Multilateral Elucidation of Islamic Trends in South Asia: History, Thought, Literature, and Politics, 2010.)。本研究は、近現代南アジア・イスラームを正しく評価するため、つまり前述の二重の周縁化を克服するための基盤を築くために、南アジア・イスラームをめぐる出版文化を調査し、データを蓄積することにしました。
本研究で明らかになった内容
本研究が対象とする南アジア諸語イスラーム文献(出版物)には南アジア・イスラーム、ひいては南アジア独特の事情が反映しています。イスラーム世界では写本の伝統が強かったため、自発的に出版を本格的に導入するのは、ヨーロッパや中国などと比べてかなり遅く、19世紀末から20世紀初めにかけてです。南アジアでも事情は似ていますが、出版の導入はエジプト、トルコ、イランなどより若干早く、19世紀初めにさかのぼります。これは、インドのムスリムが自発的に出版を導入したのではなく、1800年に東インド会社がカルカッタにイギリス人書記官養成機関であるフォート・ウィリアム・カレッジ(Fort William College)を設立し、南アジアの現地語および習慣を学習する目的で教科書を編纂する過程において「ヒンドゥスタニー・プレスHindustani Press」が同時に設置され、アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語などの刊行物が大量に発刊されたためでした。『アラビアン・ナイト』の底本として定着しているのも、このカレッジから1802年以降に刊行された版なのです。学術語としてのウルドゥー語が前面に出てくるのはこうした出版文化を背景としています。そしてその事情により、図らずも南アジアはイスラーム世界の先進地域となるのです。それ以前に南アジアで学術語として使用されたのは主にペルシア語、少し頻度を落としてアラビア語であり、デリー・スルタン朝、ムガル朝の支配層がテュルク系民族であったことからテュルク系チャガタイ・トルコ語が若干使用されました。
このような背景を元に、本研究では、次の3つの問いをたてました。
(1)出版文化が生じることによってペルシア語・アラビア語などからウルドゥー語へと主役が移る際に、いかなる文献がウルドゥー語をはじめとする南アジア諸語に翻訳され、出版されたのか。これは、アラビア語やペルシア語(そしてチャガタイ・トルコ語)文献の何が取捨選択されて南アジア・イスラームの伝統として受け継がれたか、という問いにつながります。
(2)どの出版社でいかなる南アジア・イスラーム文献は、南アジア諸語のうちのどの言語を使って出版されてきたのか、そしてそうした印刷所はだれが担っていたのか、そうした出版物は何を対象としているのか。
(3)19世紀初めから出版されてきた南アジア諸語イスラーム文献は、どこに流通したのか
(1)については、宗教書や物語文学が代表的なものだということが明らかになりました。
アキール文庫に所蔵されているウルドゥー文学史(Jamil Jalibi, Tarikh-e Adab-e Urdu 等)の一連の研究書によって、南アジアでは15~16世紀ごろから、アラビア語やペルシア語の宗教書がrisalaの体裁で翻訳されていたことがわかります。
また、物語文学に関しては、元来サンスクリット語で書かれたSukasaptatih (『鸚鵡七十話 インド風流譚』田中於菟弥訳、平凡社東洋文庫、1963)が、14世紀初めにペルシア語に翻訳されてTuti Namehとなりますが、前述のとおり、19世紀初めにイギリス人が簡明な北インドの口語体(ヒンドゥスターニー語=ウルドゥー語)の教科書を編纂するうえで、これをハイダルバフシュ・ハイダリー(Haidar-Bakhsh Haidari)という文人を使ってTotaaa Kahani『鸚鵡物語』として刊行させたことなどが知られています。
アキール文庫には、こうしたアラビア語やペルシア語からウルドゥー語への翻訳の過程に関する文献、研究書が豊富に所蔵されているほか、南アジアで執筆されたトルコ語文献、ペルシア語文献(スーフィー伝記、詩集等)も所蔵されています。
また、ムガル朝期には、上に述べたペルシア語・アラビア語・トルコ語だけでなく、サンスクリット語からの翻訳もさかんに行われていたのでした。
現代の南アジアが、南アジア固有の諸言語や英語による多言語空間である、という事実は周知のことですが、実は1世紀近くさかのぼると、アラビア語、ペルシア語、トルコ語といった西アジアの諸言語もこの多言語空間に含まれつつ、それらの翻訳活動が行われていたことが、本文庫所蔵の文献を検証することによって明らかとなりました。
(2)については、本データベースに時空間検索の機能を備えることにより、個別の事例を調べることが可能となりました。
この際、ムスリムの経営する出版社からイスラーム文献が出版されるとは限らず、またムスリムが必ずムスリムの言語と見なされるウルドゥー語やベンガル語で文献を出版するとも限らないといった例があることに留意しなければなりません。ヒンディー語で書かれ出版されたイスラーム文献が少なからず存在するからであり、アキール文庫にはこのような書籍も少なからず収められています。
(3)については、東南アジアが最も多く流通した地域ですが、ほかにもアラブ諸国や東アフリカなどが含まれることが分かりました。
アキール文庫にある19世紀半ば以降のイスラーム復興に関する研究書によって、デーオバンド学院への東南アジアからの留学生が、ウルドゥー語で学んだ知識を祖国に持ち帰り、復興運動を展開した経緯が明らかとなるうえに、マウドゥーディーの書簡集等によって、彼の著作がアラビア語に翻訳されたことも実証的に示すことができます。

アキール文庫とは、京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科が元カラーチー大学ウルドゥー文学研究科長のムイーヌッディーン・アキール博士(Dr. Saiyid Mu`in al-Din Aqil)の膨大な個人蔵書を受け入れた南アジア諸語イスラーム文献を中心としたコレクションです。
アキール文庫の詳細に関しては、「京都大学アキール文庫について」(イスラーム世界研究 第7巻 2014年 3月 143-151 頁)で述べられているので、関連論考をご覧下さい。
また、アキール文庫に含まれる資料の分類に関しては、マニュアル等にある該当文書を、特徴的な分類項目に関する解説は解題をご覧下さい。
アキール文庫の詳細に関しては、「京都大学アキール文庫について」(イスラーム世界研究 第7巻 2014年 3月 143-151 頁)で述べられているので、関連論考をご覧下さい。
また、アキール文庫に含まれる資料の分類に関しては、マニュアル等にある該当文書を、特徴的な分類項目に関する解説は解題をご覧下さい。